コロニー設計において、気体フィルター使っていますか?
今回は、手軽にお安く気体の仕分けができる方法を使った水素発電所を作っていきます。
気体フィルターを使わない仕分け
代替手段との消費電力比較

「気体フィルター」は、「気体パイプ元素センサー」+「気体遮断器」でも似たような挙動結果を得ることができます。
消費電力は120W vs. 10Wなので、同じ結果が得られるのであれば、当然後者を選びます。
実際にできるのか動画で確認
まず動画に簡単にまとめました。
作成する際の注意点として、「気体遮断器」の中(2マスの中央部分)はパイプを繋がないで下さい。
※再生すると音声が出ます
これだけ混ざってパイプが詰まった状況でも、たったの50Wで全ての気体分別が出来ているのが分かると思います。
もし気体フィルターで同じことをやると、120W×5で600Wも消費される計算です。
この方法はほとんどすべての気体フィルター使用場所に適用可能です。
水素発電所で実際に使用する


「電解装置」(120W)+「吸気ポンプ」×2(240W×2)+気体遮断器(10W)=610W
のシンプル構成。
気体フィルターを採用した場合は720W消費構成になり、常時稼働が前提の設備なので差は結構大きい。
多少挙動が違う点はありますが、ほとんどの場合で代替法として使えますので、必ず覚えておいた方がいいテクニックと言えます。
水素発電に関しては、吸気ポンプで水素のみを吸ってさらに電力節約する方法もありますが、自分はうまく気圧管理(気圧が高すぎると電解装置が止まってしまう)ができなくて結局シンプルな方法(2つの吸気ポンプで動作)を取っています。
画像では、気圧センサー+FILETERゲートでの気圧管理をしていますが、これは間違いで気圧センサー+BUFFERゲートゲート(FILETERゲートもあっても良い)で管理するのが正しいです。
これでも一応動きますが、気圧センサーの数値をかなり下げないと電解装置が止まってしまうので、電解装置室の作り自体はまだまだ改善の余地があります。
気体遮断器を使った分別の注意点
上の記事を見ると、「気体遮断器が万能だから気体フィルターは必要ないよね?」という感想を抱くかもしれません。
しかしながらこの分別法にも弱点があります。
それは、「パイプがスムーズに動かない状況だと分別に失敗するケースがある」ということです。
実際に運用してみると、「ここは確実に分別したい」というポイントに関しては、気体フィルターで運用した方が良い場面もありました。
とはいえ、フィルターの120W(フル稼働で1サイクル72kj)はとてつもなく重いので電力事情が厳しい序盤~中盤ではかなり有用な方法であることは確かです。
また、今回の記事では「気体」に関しての分別を行いましたが、液体に関しても同様の方法で分別可能です。
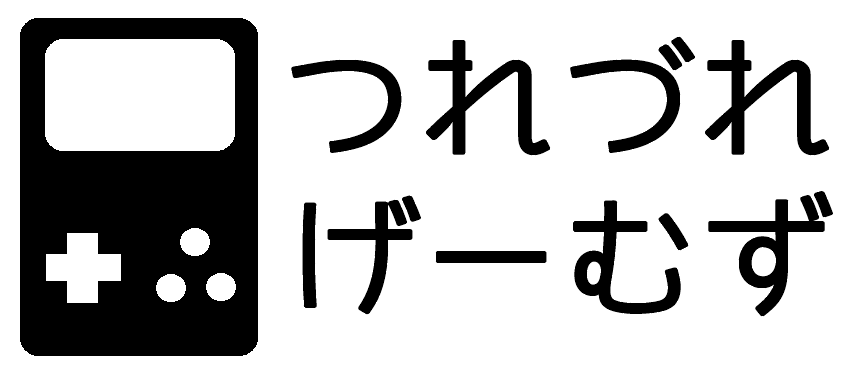
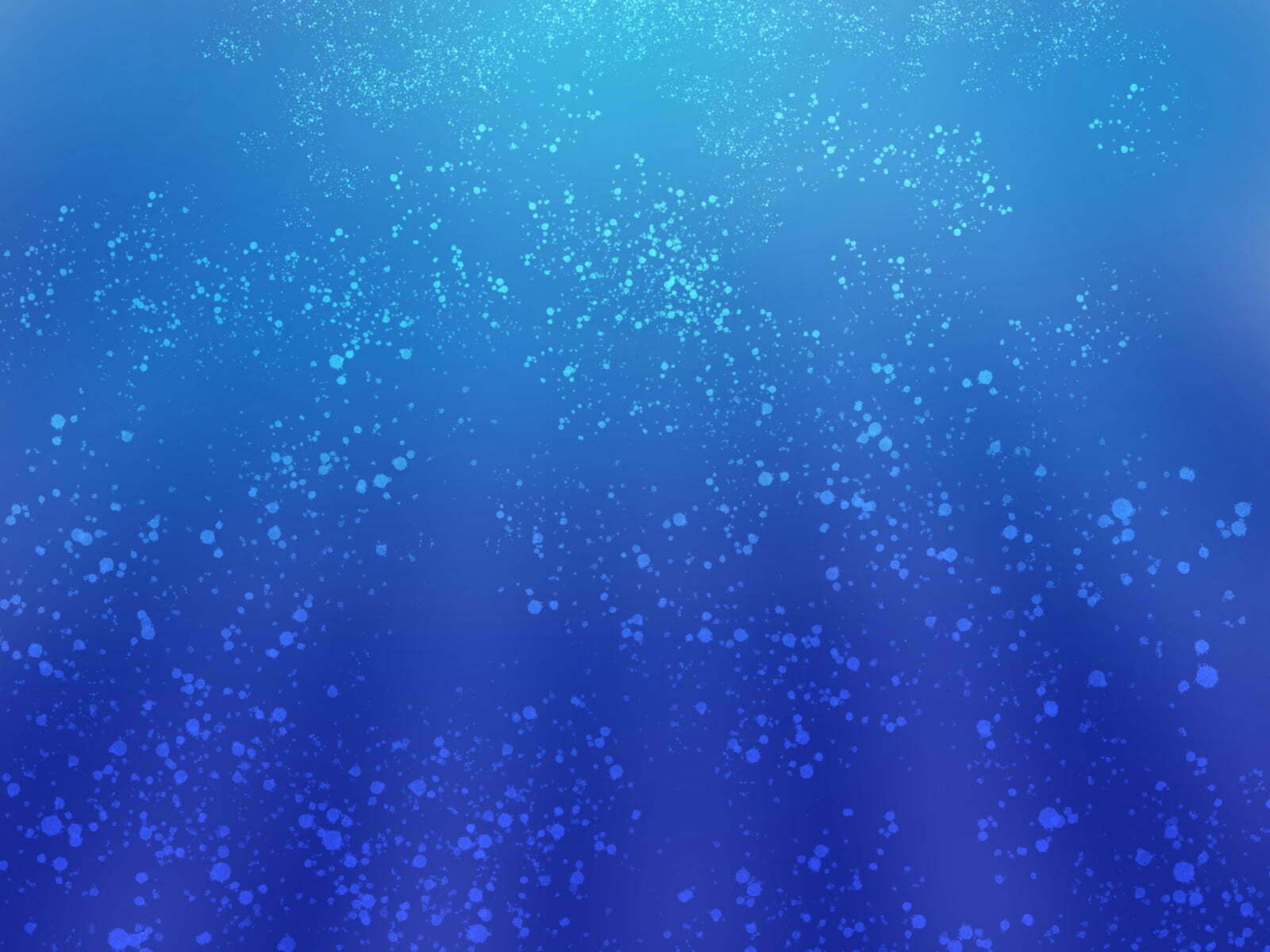
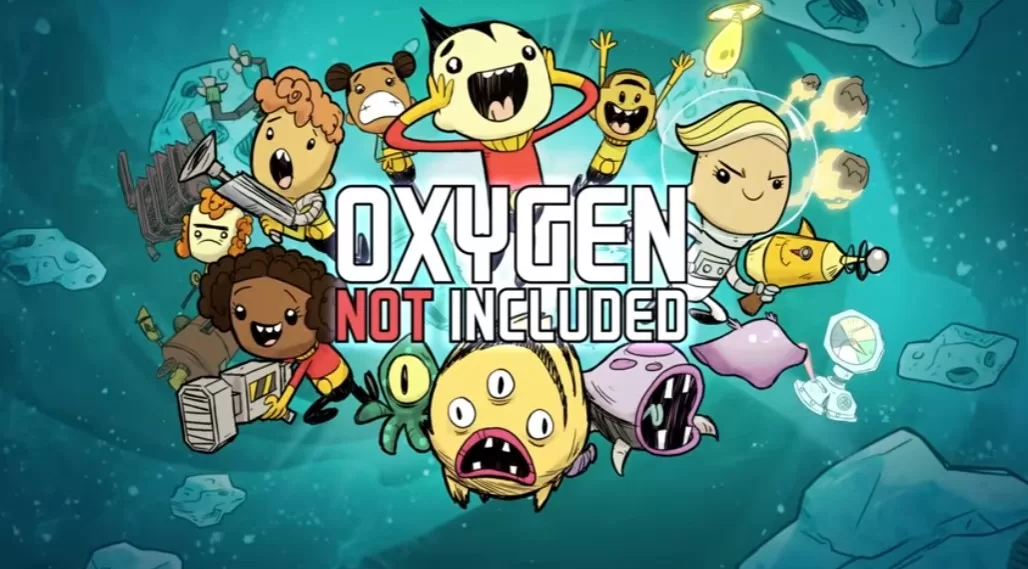
コメント